変化するものが生き残ると言いながら、人が変化できない理由
ダーウィン曰く、
「強いものや賢いものが生き残るのではなく、変化するものが生き残る」
産業構造が大きく変わりつつあるなか、あちこちの会社から
「我々も生き残るために変化しなくてはいけない!」
という掛け声が聞こえてきます。
しかし一般的に、現状維持と前例踏襲の鎖を外し、変化する事はとても難しい事です。
ゆえに、イノベーションのジレンマは数ある歴史的な優良企業を屠ってきました。
まず、人間は心理的に現状維持を求めるという事を知っておく必要があるでしょう。
損失回避バイアスにより、何かを変える事による損失を過大に評価してしまう。
不作為バイアスにより、とりあえず今の延長線上を選択しがちになる。
確証バイアスにより、「そうさ、今のまま頑張ればなんとかなるさ!」という希望的観測が強化される。
だから、人は大きな変化を避け、今のままの行動を維持しがちになるというのが普通なんです。これが現状維持バイアスです。
現状維持バイアスは、会社のビジネス転換を非常に難しくしたり、個人の転職や起業や結婚をためらわせたり、新しい事へのチャレンジに心理的ブレーキをかけてきます。
現状維持バイアスから脱却するには?
いや、私もよくわかりませんけど(笑)
1.動機の明確化
2.目的の設定
3.定量的な分析
ってところかな!
1の動機は、そもそも現状に満足しているなら別に現状維持で良いわけで、少しでも変えようと考えるなら、不満なり不安なり危機感なりがあると思います。まずはそれを明確にする。
では、どのような状態であることが望まれるのか?どうすれば不満や不安は消えるのか?これを設定するのが2です。定量的な目的であればさらに良いでしょう。
3つめの定量的な分析は、まず動機や目的が理にかなっているものなのかを確認する必要がありますし、次のステップとして「どうやって目的を達成するのか?」を数字的なストーリーで語れれば安心です。
とはいえ、未知なものに挑もうというのであれば、定量的な分析にこだわりすぎるのもNGですね… 世の中にないものにはデータがないので、フェルミ推定でガンガン進みましょう。
順番にステップを踏むというよりは、1~3をサイクルで回して修正する柔軟さが必要に思います。
…なんて事を書いてみたものの、自分も現状維持の誘惑から逃れられない身であれば、ゆでガエルにならないことを願いながら筋トレに励むものであります。
ともあれ、各種の認知バイアスは人間が誕生した時からずっと持っているものだから、それを把握して上手く付き合っていくしかないですね。
それでは今日はこの辺で (^^)/~~~
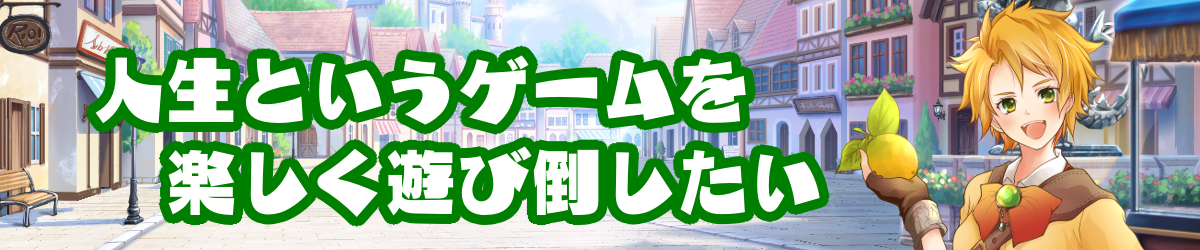



コメント