精神科医の樺沢紫苑さんが書いた、良質な学び(インプット)を得るための本。
個人的評価は★5。一読の価値あると思います。
この本は、同氏が2018年に出した「学びを結果に変えるアウトプット大全」の続編的な位置づけですが、後述するようにインプットとアウトプットは表裏一体のものなので、併せて読むと大変勉強になるかと思います。
本書は7つのCHAPTERと80の小項目からなっていますが、自分に刺さったポイントを中心に紹介します。
私が本書で特に参考にしたいと思ったポイントは、ざっくり下記の3つです。
1.アウトプットを前提としてインプットする
2.「観察力」を磨く
3.不要な情報をカットする
なお、本書の「学びを欲張らない」という項目の中で、「気づきは3つ得られれば十分」という話があります。私も上記の3つを習慣化できてから、新しい3つにチャレンジしたいと思う次第。
アウトプットを前提としてインプットする
この本の「はじめに」に書いてあり、前書「アウトプット大全」はずっとこれを論じているのですが、アウトプットを前提としたインプットは、その学習効果が飛躍的に高まります。
出張で何かの見学に行った時、上司に「帰ってきたら100人の前でプレゼンね♪」とか言われていたら、メモもしっかりととって資料も可能な限り集めようとするでしょう。
これと同じことを普段の生活に取り入れれば、趣味も大事なインプットになるってわけですね。
例えば映画を観る時には、その感想をブログにアップする事を前提にして観ると細部まで気がついたり、内容が記憶に残りやすくなります。
思えば、私がブログにあまりPVの増えない書評をのせているのも、これを無意識に実践していたんだなあと感じます。
書評を書くことを意識していると、自然とその本のキーポイントを整理して読もうとしますし、大事なポイントは覚えておこうとします。
これは、良質な学びに他なりません。よっしゃ、サボらずにちゃんと書評書こうっと!
「観察」することの重要性
著者はシャーロックホームズの大ファンのようで、ホームズが初対面のワトソンの職業を当てたシーンが大好きとの事です。
推理を可能にしたのは、ホームズの非常な観察力。
私は探偵ではないので、人の職業を推理を当ててもドヤ顔するくらいしかできないのですが、企画屋の端くれとしては「観察によってさまざまな疑問に気づく」事はとても大切だと感じます。
「なぜカレーに入っているナスは素揚げしてあるのか?」とか不意に聞かれても、そもそも観察によってナスが焼いてあるのか揚げてあるのかを認識していないと疑問すら持てないし、チコちゃんに「ぼーっと生きてんじゃねえよっ!」て怒られるのも一理あるような気がしてきます。
そして観察(Observe)から始まるOODAループは、開発や企画の仕事をされている人にはPDCAサイクルよりもしっくりとくるんじゃないでしょうか。
観察(Observe)
仮説構築(Orient)
意思決定(Decide)
実行(Act)
※本書では「見る」⇒「わかる」⇒「決める」⇒「動く」と簡単な書き方になっています。
ジロジロ見過ぎて嫌がられない程度に、人も事象も観察していきたいと思います!
不要な情報をカットする
”ニュースの8割は自分にとって不要”
”そもそもニュースを読む、見る事は必要なのでしょうか?”
確かにそうですね。
特にテレビのニュースはデメリットが多く、ネガティブなニュースや偏った考え方を押し付けてくるので元からあまり見ないようにしていましたが、ネットで見るニュースも別にそれほど役立っているわけじゃないな~
芸能人のゴシップとかスポーツの結果とか、僕には本当にどうでもイイもんね!
誰でも時間と脳のリソースは有限なので、(多少のエンタメ要素は必要としても)不要なニュースはなるべく省きたいもの。
本書では、有用な情報が自然と入ってくるシステムの構築法なんてのも載ってますのでご参考にどうぞ。
あと個人的に、最近Youtubeで動画を楽しんでいるときに、おススメ動画でウザいインフルエンサーによる「これであなたもお金持ちになれる」みたいなウザい動画が上がってくるのでマジウザい(←語彙力)ですが、ちゃんと「興味ない」とフィードバックするとAIが学習して宣伝してこなくなったので覚えておくと吉。
それからちょっと余談ですが…
項目64 病気から学ぶ。コレ。
病気になったときにすべきことは、自分や他人を責めるのではなく、病気を受け入れること。そして、「なぜ病気になったのか?」という問題と向き合い、自分なりの答えを出す。つまり、「病気から学ぶ」ということです。
沁みる… 沁みるわあ…
という感じで本書、良質な学び方を体系づけて説明してくれているのでとても読みやすく、項目もいっぱいあるので、「自分にぴったりのヒント」が見つかるんじゃないかと思います。多分。
Easy oar.
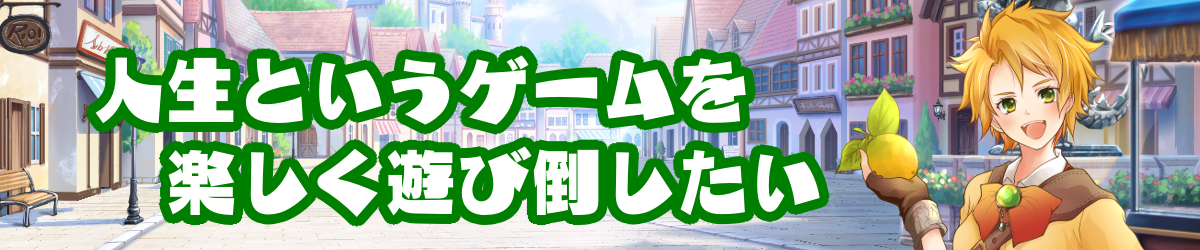
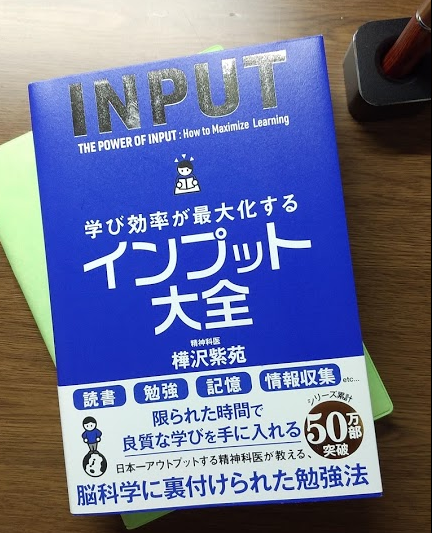


コメント